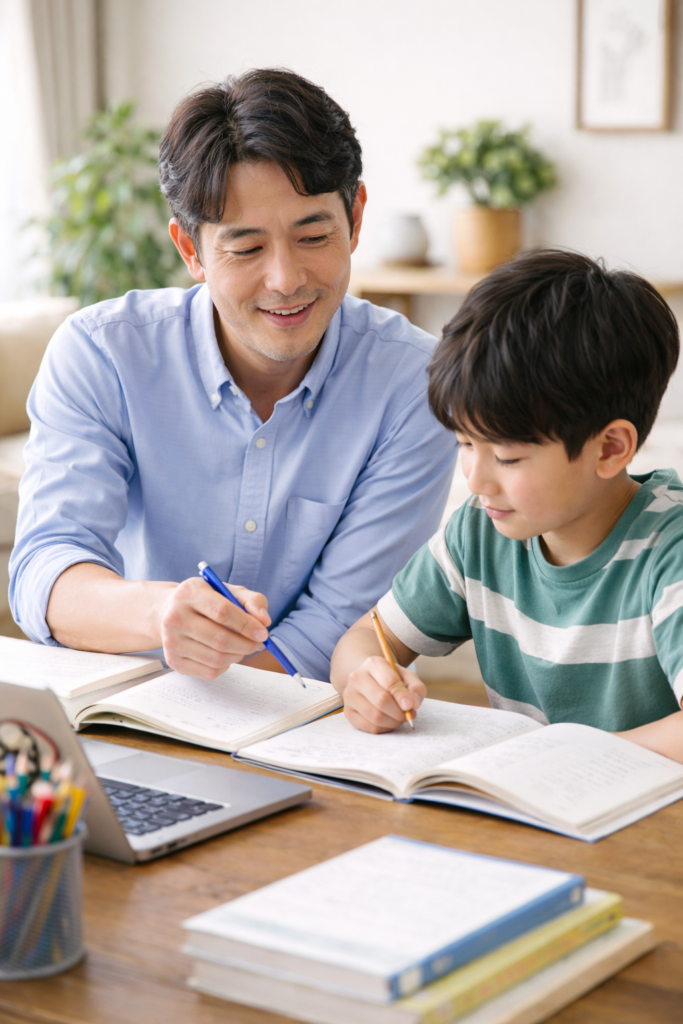
はじめまして・・
私は、成城学園駅前で塾長歴30年の熟練学習指導者です。 生徒さん一人ひとりに合わせた丁寧な指導を心がけています。
これまで、数学・英語を中心に小学生から高校生まで幅広く指導経験があります。勉強が苦手な生徒さんには基礎から丁寧に、得意な生徒さんには応用力を伸ばす学習指導を行います。
「わかる楽しさ」を大切にしながら、勉強への苦手意識をなくし、自信を持って学習できるようサポートします。
地元密着(町田市 木曽東 森野)の家庭教師として、安心して相談いただける存在になれるよう努めます。よろしくお願いいたします。
Q1.どのような家庭教師ですか?
算数・数学を専門に指導している家庭教師です。
(英語・理科なども)並行して指導します。
長年、学習塾および家庭教師として多くの生徒を指導してきました。
「勉強が苦手」「どこから分からなくなったのか分からない」
そうしたお子さまが、もう一度、安心して学び直せる場所を作ることを大切にしています。
Q2.どんな生徒さんを対象にしていますか?
主に、次のような生徒さんを対象にしています。
- 算数・数学に苦手意識がある小・中・高校生
- 学校の授業についていけなくなった生徒さん
- 不登校・別室登校・登校しぶりのあるお子さま
- 基礎から丁寧に学び直したい生徒さん
- 中高一貫校に通っているが数学・英語・理科の進度が早くて困っている
「成績を一気に上げたい」というより、
まずは理解を積み重ねたいというご家庭に向いています。
Q3.指導で一番大切にしていることは何ですか?
「分からないまま先に進ませない」ことです。
算数・数学は、途中の理解が抜けたまま進むと、
必ずどこかで行き詰まります。
私は、
- どこまでなら確実に分かっているか
- どこでつまずいたのか
を丁寧に確認し、必要があれば学年をさかのぼって指導します。
Q4.授業はどのように進めますか?
一人ひとりに合わせて進めます。
- 図やイラストを使った説明
- 身近な例に置き換えた説明
- ノートの書き方・考え方の整理
「教える」よりも、一緒に考える時間を大切にしています。
Q5.不登校の子どもでも大丈夫でしょうか?
はい、大丈夫です。
不登校のお子さまの場合、
まず必要なのは「安心して話せる関係」です。
- 無理に勉強させない
- 急がせない
- 比べない
この姿勢を大切にしながら、
少しずつ「できた」「分かった」という経験を積み重ねていきます。
*2025年度の大学受験では・・ これまで不登校であった生徒を立命館大学・アジア太平洋大学に合格させてます。指導科目は数学、英語、論文、面接の受け方などでした。
Q6.成績は本当に上がりますか?
短期間で劇的に上がることもありますが、
多くの場合は、ゆっくりと確実に上がります。
基礎を固め、理解を積み重ねることで、
テストの点数や授業の理解度に自然と変化が表れてきます。
Q7.保護者とのやり取りはありますか?
はい、重視しています。
授業の内容だけでなく、
- 学習の様子
- 気持ちの変化
- 今後の進め方
などを、保護者の方と丁寧に共有します。
Q8.体験授業や相談はできますか?
はい、可能です。
「いきなり始めるのは不安」という方のために、
事前のご相談や体験指導をおすすめしています。
Q9.最後に、保護者の方へ一言お願いします。
算数・数学が苦手なのは、才能の問題ではありません。
分かる順番が合っていなかっただけということがほとんどです。
お子さまのペースを大切にしながら、
「分かる」「できる」という感覚を一緒に取り戻していきましょう。